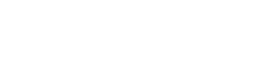2024年も終わりに
2024年も暮れを迎え、地震の多い日本で暮らしていることを改めて実感する一年となりました。今年1月には石川県能登地方で地震が発生し、復興が未だ進行中です。また、南海トラフ地震に関する臨時情報も発表され、防災意識がさらに高まった年でもありました。
私たち株式会社sqced(サクシード)も、こうした状況を受け、電気工事業者として地域社会にどのように貢献できるのかを真剣に考える一年となりました。

地震後の課題と当社ができること
地震は建物の倒壊だけでなく、火災やライフラインの停止など、私たちの生活に多大な影響を与えます。特に、地震後に発生する火災の多くが電気火災によるものです。建築設備工事管理会社として、当社では以下の取り組みを検討しました。
1.工事事業者の存在が鍵
復興には多くの現場業務会社が必要となり、当社も建築設備工事管理会社として知名度を上げて、知ってもらうことにより、地震時には復興の一助になると確認しています。
2. 地域を超えた支援体制の構築
地震が発生した際、地域内の工事業者が被災すると、復興支援が滞る可能性があります。そのため、当社では県内でも離れた場所の企業様との関係性を強化するため、営業活動の範囲を広げていきます。
3. 電気火災の予防対策
電気設備の専門家として、電気火災の原因を未然に防ぐ方法のうちの一つ「感震ブレーカー」の普及を進めています。

当社が取り組む感震ブレーカー普及の必要性
感震ブレーカーは地震発生時に自動的に電力を遮断し、電気火災を防ぐ装置です。兵庫県南部地震以降、防災対策として注目されているものの、実際の普及率は非常に低い状況にあります。内閣府の調査によれば、設置率はわずか6.6%にとどまっています。
地震後の火災を防ぐ重要な装置
地震後の火災原因の半数以上が電気に起因しているため、感震ブレーカーの普及は電気火災を防ぐために極めて有効です。特にアパートなど集合住宅や木造住宅、飲食店が密集する地域では、その効果が期待されています。

普及に向けた課題
感震ブレーカーの普及には多くの課題があります。以下に主要な課題をまとめました:
- 認知不足
多くの人が感震ブレーカーの存在を知らず、その必要性を理解していません。 - 高額な導入費用
配電盤設置タイプは比較的高価であり、各家庭で設置に踏み切れない状況です。 - 効果の実感が乏しい
家具の転倒防止は分かりやすい効果がある一方で、感震ブレーカーの効果は目に見えにくい点が課題です。 - 周囲の家屋の影響
自宅で設置しても、周囲の家屋からの火災リスクを完全には防げないため、設置の動機が弱い場合があります。 - 設置に伴う負担
工事には時間がかかり、立ち会いや対応が必要になるため、またどこに頼めばよいかわからず、導入のハードルが高く感じられます。 - 政策支援の不足
国は設置を推奨しているものの、自治体の財源が限られており、補助金や助成金が不十分です

当社の取り組みと未来に向けた計画
普及の課題を踏まえながらも、当社では感震ブレーカーの導入を積極的に推進し、電気火災という二次災害の防止に取り組んでいます。具体的な活動として以下を計画しています:
- 産業まつりでのブース出展
来年の豊山町商工会の産業まつりにてブースを設け、感震ブレーカーの実物を展示し、その効果を来場者に広く伝えます。 - 動画を活用したセミナーの開催
TMdesign制作の解説動画を活用し、感震ブレーカーの必要性やメリットを分かりやすく伝えるセミナーを企画しています。 - メーカーや代理店との連携強化
電気商材に関する情報を集め、メーカーや代理店との協力を通じて、より効果的な普及活動を目指します。 - 住宅以外への普及拡大
集合住宅や木造住宅だけでなく、小型店舗などの商業施設にも普及を推進。不動産業を通じた普及活動にも力を入れています。
まとめ
日本は地震の多い国です。災害による被害を最小限に抑えるためには、感震ブレーカーの普及が欠かせません。当社は地域社会の安全と防災対策に貢献するため、これからも積極的に取り組んでまいります。感震ブレーカーや防災に関するご質問がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。